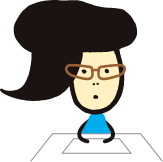
石川テレビニュース
ISHIKAWA TV NEWS
石川県内ニュース
「能登にどうやって人を残すか」「能登にどうやって人を呼び込むか」二つの課題に金大の青木准教授に聞く
ここからは現在の被災地の課題と解決策について青木さんとお話を進めていきます。地震から1年半、青木さんが考える被災地の課題は何でしょうか?
青木さん:
大きく分けて2つあります。一つは「どうやって能登に人を残すか?」もう一つは「どうやって能登に人を呼び込むか?」です。最初の課題は、地震発生以降繰り返し語られてきたテーマですが、いま改めてその重要性が問われています。そして2つ目の課題は、インフラも徐々に復旧してきた今、特に重視したいテーマだと思います。
では一つ目のテーマですが、どうやって能登に人を残すか。被災地の人口流出について、まとめました。県によりますと、去年1月1日時点の人口と先月1日時点の人口を比べると、能登地域では約1万500人、減少しました。中でも輪島市や珠洲市など奥能登4つの市と町は、地震前より6100人あまり、率にして11パーセントと大きく減少しました。やはり奥能登の人口流出が続いています。
こうした中、被災者が今、最も気にしているのが災害公営住宅です。県は災害公営住宅を3000戸必要とみているようですが、仮設住宅に現在入居している方の声を聴きました。
輪島市の仮設住宅「マリンタウン第一団地」で自治会長をしている橋爪和夫さんです。地震から1年半が経ち、住民の間で住まいについての不安が広がってきているといいます。
橋爪さん:
「輪島に残ろうか迷ってきたという人もいるこれは前と温度差があって前は絶対に残るって人が多かったんですよもうちょっと具体的なものが欲しいなという宙ぶらりんの状態が続いているのでこの1年半という中でちょっと心境の変化が出てきている気がします。」
この仮設住宅に入居が始まったのは県内で最も早い去年2月。2年の退去期限は延長が決まりましたが、災害公営住宅に入居する見通しは立っていません。さらにこんな課題も…
橋爪さん:
「朝市地区って都市計画に入っているうちらとしてみれば土地があるから家を建ててもいいのかというとダメなんですよ。」
橋爪さんをはじめこの仮設住宅に入居している人の半数ほどが火災で消失した朝市通り周辺に住んでいた人たち。
更地となった土地があるものの、市の復興計画の中心とも言えるこのエリアでは区画の整理が終わらないと家を建てることができないとというのです。
橋爪さん:
「2年先に『はい(建てても)オーケーです』と言われた時に(住宅再建の)助成金の期限が切れてしまったら建てられないじゃないですかあれを頼りに建てようと思った人がそんなんならば違うところに建てるわとなるわけですよ。」
具体的な再建のスケジュールが立てられない状況で橋爪さんは地元を離れる人が増えることを懸念しています。
橋爪さん:
「みんな輪島好きなんですよこんな姿になってもやっぱり地元に残りたいという気持ちはあるんだけどいかんせんお金もかかる話だし自分たちは年齢のこともあるし思いだけではおれないというか…」
青木さん:
「輪島に残りたいと何とか頑張ってきたが、このままでは輪島を離れざるを得ない人も出てくる」という言葉は重いなと感じました。特に朝市の焼失地区は、新しい町の形が固まるまで時間がかかりますですので行政側には、「どれだけ待てば、どういう形で戻れるのか」という具体的なイメージを分かりやすく伝えて住民の不安を払拭するよう努力してほしいと思います。人口流出によって、能登各地では福祉施設の担い手不足などの暮らしに関する深刻な問題が起きています。特に子育て世帯の流出は、今後の復興に向けても大きな足かせとなりますので早急な対応を取っていかねばならないと思います。
さらにもう一つのポイント「能登にどうやって人を呼び込むか」も大きな課題ですね。
青木さん:
私もおととい、珠洲で活動する団体の方と話をしてきましたが、とても前向きでした。先ほども申し上げた「能登に人を残す」には、生業が成立することが不可欠です。能登に関するニュースが少なくなってきている中、こうした地元の皆さんの頑張りを生かすためにも、お客さんに来てもらえるような情報発信が必要だと実感しました。県でも能登の各被災地や震災遺構を巡る修学旅行の誘致、「能登地域のジオパーク化を目指す」ための予算も今年度ついていますので、今後の推移も見守りたいところです。
震災遺構については、先日、珠洲市のさいはてのキャバレーがそうだったようにさまざまな声がありますね。
青木さん:
そうですね、宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎については、保存か解体かで意見が割れ、ようやく去年、町が震災遺構として保存することになりました。住民どおしで意見が分かれる場合は拙速に判断せず、今後しこりを生まないように時間をかけて議論していくことも大切なのではと思います。何より重要なのは、現地の情報を伝え続けることそして我々が被災地のことを忘れないこと。メディアの皆さんにもぜひお願いしたいと思います





