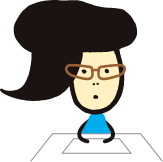
石川テレビニュース
ISHIKAWA TV NEWS
石川県内ニュース
能登半島地震巡る県の初動対応 どこが「受け身」とされたのか 発生後の職員出勤率や市町の意見から如実に
能登半島地震の初動体制について検証をしてきた委員会は報告書で「県の対応が受け身」だったとありました。
例えばこちらが地震発生後の県職員の出勤率のグラフです。
県庁全体の出勤状況は50パーセントを下回る日もありました。しかし危機管理室や土木部といった一部の部局では出勤率が高くなっています。
一部の部局や職員に負荷が集中していました。
報告書では、「全庁体制で対応する意識が希薄だった」としてあらかじめ、他部署の応援体制を明確にしておくことなどが改善策として示されました。
この「受け身の姿勢」、被災した市や町からも厳しい声があがっています。
県は職員をリエゾン、つまり県との調整役として市や町に派遣しました。
しかし、現場からは「リエゾンは指示がなければ動かず何をしているのかわからなかった」「相談しても『市や町の仕事』との返事が多く県で何ができるかを検討してほしかった」といった声があがっています。
中には「次長級が派遣されたことで県への要望が伝わりやすくなった」という声もありましたが、リエゾンの役割を明確にしてマニュアルを整備することが改善策として示されました。
今回の報告書は県に向けてですが民間企業も含めて自分たちの組織はどうあるべきか考えるヒントが詰まっていると思います。
災害はいつ起きるか分かりません。出来うる限りの想定と準備をすることが私たちも大切です。
この報告書は県のホームページで確認できます。





