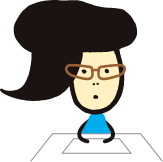
石川テレビニュース
ISHIKAWA TV NEWS
石川県内ニュース
「住める状態に戻すのは難しい」のか? 能登の古民家、解体か活用か
能登半島地震から約1年4カ月、被災地では公費解体が進み、景色が変わりつつある。県内での解体申請は約4万棟にのぼり、4月末時点で約65%が完了した。公費解体の申請期限は地域によって異なり、能登町と輪島市はすでに終了。珠洲市と志賀町は6月末、七尾市は8月29日までとなっている。
志賀町富来地域にあった北陸中日新聞記者の父の実家も被災し、母屋が半壊、蔵や納屋は全壊と判定された。
「住める状態に戻すのは難しい」と判断し、
去年春に公費解体を申請。ほぼ1年後の今年3月に解体され、更地になった。
「本当に父の実家があったところなのか」と目を疑う状況だったという。
解体すべきか、修繕して活用すべきか迷った場合、県は所有者に「解体の留保」を市町に申し出るよう呼びかけている。留保した建物は10月末完了目標の公費解体と別枠となり、申請期限後に「やはり解体しよう」となっても解体できる。
専門家の助言は大切だ。
県は全国古民家再生協会や建築設計の専門家らでつくる能登復興建築人会議などと連携し、去年12月から相談窓口を設置。これまでに400件ほどの相談があった。
建築人会議は被災地を回り、修繕や保存活用の可能性を調査し、集落単位での活用などを検討する業者の視察ツアーも実施している。
県によると、50件以上の被災家屋が全国の古民家を紹介する情報サイト「古民家住(す)まいる」に掲載され、契約がまとまれば活用されることになる。
さらに県は、被災家屋を修繕し活用を検討する事業者への財政支援も検討中だ。
創造的復興につながる活用を増やす狙いがある。
大きく分けると、自ら修繕し住み続ける場合と他者の活用を希望する場合があるが、手続きに半年から1年ほどかかる見込みだ。最終的に公費解体となる場合もあるが、後悔しないように県・創造的復興推進室などに相談してみることも大切になる。





